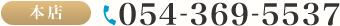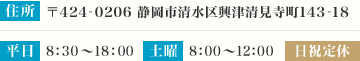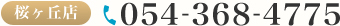2020年12月号お酒との上手な付き合い方
これから年末年始にかけて、お酒を飲む機会が増える方も多いのではないでしょうか?
アルコールは少量なら気持ちをリラックスさせたり会話を増やしたりする効果がありますが、大量になると麻酔薬のような効果をもたらし、運動機能を麻痺させたり意識障害の原因になります。
アルコールの吸収と分解
体内に摂取されたアルコールは、胃や小腸上部で吸収されます。吸収は全般的に速く、消化管内のアルコールは飲酒後1~2時間でほぼ吸収されます。アルコール分解の最初のステップは主に肝臓で行なわれ、その後は筋肉が主体となります。
飲酒後血中濃度のピークは30分~2時間後に現れ、その後濃度はほぼ直線的に下がります。アルコールの消失(分解)速度は個人差が非常に大きいことが知られていますが、その平均値は男性でおよそ1時間に9g、女性で6.5g程度です。アルコールの吸収や分解には多くの要因が関係しています。
12の飲酒ルールとは?
厚生労働省のガイドラインや様々な研究結果を踏まえて、以下に健康を守るための飲酒ルールを設定します。ご自身の飲み方を一度振り返ってみましょう。
- 飲酒は1日平均2ドリンク以下
- 女性・高齢者は少なめに
- 赤型体質も少なめに
- たまに飲んでも大酒しない
- 食事と一緒にゆっくりと
- 寝酒は極力控えよう
- 週に2日は休肝日
- 薬の治療中はノーアルコール
- 入浴・運動・仕事前はノーアルコール
- 妊娠・授乳中はノーアルコール
- 依存症者は生涯断酒
- 定期的に検診を

適量を知り、飲み過ぎに注意しましょう!
厚生労働省は「健康日本21」の中で「通常のアルコール代謝能を有する日本人においては、節度ある適度な飲酒として、1日平均純アルコールで20g程度である。」と定義しています。20gとは大体「ビール中ビン1本」「日本酒1合」「チュウハイ(7%)350mL缶1本」「ウィスキーダブル1杯」などに相当します。
また、アルコールは糖尿病や脂質異常症、高尿酸血症などの様々な疾患と密接に関係しています。以下の表を参考に、適量を知りましょう。
尿酸値が高いといわれた方は、適量の乳製品を摂ることで血清中の尿酸値が低下したというデータがあります。
【酒類のエネルギー(kcal)と糖質量(g)】
| アルコール度数(%) | カロリー(kcal) | 糖質(g) | ||
| ビール | 350mL缶 | 4.6 | 140.0 | 10.9 |
| 発泡酒 | 350mL缶 | 5.3 | 157.5 | 12.6 |
| ワイン | グラス2杯(200mL) | 11.4 | 146.0 | 4.0 |
| 焼酎 | 1杯(60mL) | 25.0 | 131.4 | 0 |
| 日本酒 | 1合(180mL) | 16.5 | 196.2 | 8.8 |
| ウイスキー | シングル1杯(30mL) | 40.0 | 83.0 | 0 |
\寒い冬にピッタリ/
鶏肉とさつまいものクリーム煮

| エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 糖質 | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|
| 447kcal | 24.5g | 17.4g | 43.4g | 2.4g |
※栄養価は1人分です
【材料(2人分)】
・とりもも肉…150g
・バター …15g
・サツマイモ …150g
・たまねぎ …1/2個
・しめじ …50g
・牛乳 …300ml
【調味料A】
・コンソメ…小さじ1
・砂糖 …小さじ1
・味噌 …小さじ2
・コショウ…少々
・水…100ml
・パセリ…少々
〈作り方〉
1.鍋を中火にかけてバターをしき、とりもも肉を加えて表面に焼き色がつくまで焼く。
2.サツマイモ、玉ねぎ、シメジを加えて炒め、玉ねぎがしんなりしてきたら火を止め薄力粉を加え混ぜる。
3.弱火で粉っぽさっぽさがなくなるまで炒めたら、牛乳を少しづつ加えながら混ぜ、とろみをつけていく。
4.器に【調味料A】と「3」のスープを少し入れて混ぜ合わせ、調味料が溶けたら「3」に加えて混ぜる。
5.「4」に水を加えて混ぜ、弱火で10分程煮込んだら、器に盛り付けパセリをちらす
参照HP「eヘルスネット-飲酒」https://www.e-healthnet.mhlw.go.jp/information/alcohol
「ソラレピ」https://recipe.shidax.co.jp/